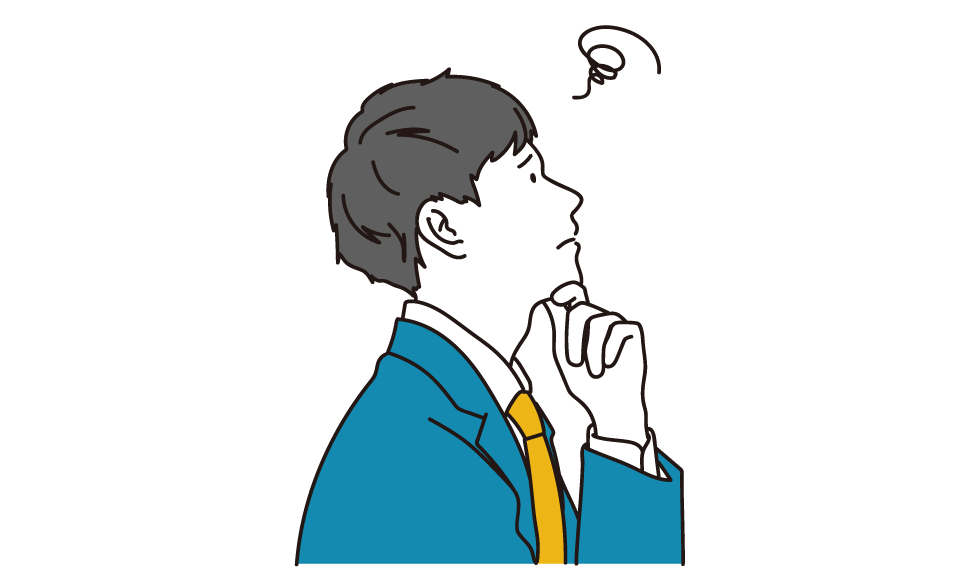今回は新築を検討するとき、多くの方が「わかりにくい」と感じる「住宅の総額」について解説していきます。
坪単価で金額の目安はよく聞くものの、実際はそれだけじゃないらしい…、でも項目も多いし、結局はうちはいくらになるの?と不安になる方も少なくないでしょう。
今回は住宅の購入価格の成り立ちをわかりやすくお伝えすると共に、だいたいコレぐらいの金額をみておけばよい、という目安まで紹介します。
それでは、今回のコラムの要点からみていきましょう。
・注文住宅の価格の内訳は、建物本体価格+付帯工事(ライフラインの工事他)+諸経費の3つで構成される
・なかなか “総額表記” ができない理由は、注文住宅では最初の時点では仕様が確定していないことに加えて、土地条件や借入プランによって変動する金額が大きいため
・費用の割合がおおよそ、「建物本体価格:付帯工事:諸経費 = 7:2:1」となることから、総額を2,800万円にする場合、建物価格 1,960万円:付帯工事 560万円:諸費用 280万円 という内訳になる ※あくまで目安
・エツサスの場合、間取り・仕様があらかじめ決まっているプランもあるため、おおよその総額表示をお伝えしながらご案内が可能
<1>新築価格の内訳

新築の総費用は「建物本体価格」「付帯工事」「諸経費」の3つに分けられます。
建物本体は住まいそのものの材料費・工事費、付帯工事は給排水などライフラインなどの周辺工事、諸経費は登記・税金・保険・設計料などの事務的な費用を指します。
まずは、この3つの内容がどんな内容なのかを見ていきましょう。
<1-1>建物本体価格

建物本体価格は「構造躯体」「内外装」「設備機器」など、実際に家を作るための主な費用です。
中身としては、構造(柱や基礎など)や外装材・断熱材・窓・床材・キッチン・浴室などによって構成される費用になります。
注文住宅ではすべて仕様を決めて初めて価格が出ますが、契約前などは一般的に住宅会社が最初の建物本体価格を算出するために便利な「標準仕様」での建物本体価格で契約することが多いです。
そのあと建築主の方の具体的な趣向で、様々なものを選んで調整した後、建物本体価格が確定します。
展示場をまわっていると、よく聞く “坪単価表示” は比較に便利なように見えますが、標準として含まれる範囲が会社ごとに異なるため内訳確認が難しいのです。
<1-2>付帯工事

付帯工事とは、「造成・地盤改良」「外構(塀・門・カーポート)」「給排水・上下水道接続」「電気引込」「ガス引込」「仮設工事」などを指します。
土地の傾斜や地盤の状態、既存インフラの有無で費用が大きく変わります。
特に地盤改良や擁壁設置、道路からの水道引き込みが必要な場合は高額になりやすいため、事前の現地調査で想定費用を把握しておくことが大事です。
<1-3>諸経費

諸経費は「設計料」「各種申請費用(確認申請など)」「登記費用」「住宅ローン関連費用(保証料、事務手数料)」「火災保険、地震保険」「印紙税や登録免許税」などです。
聞き慣れない内容が多く、相場や目安の金額も想像しにくい部分となっており、多くの方が「わかりにくい」と感じる部分の多くが、この諸費用です。
税金や手続きの費用は地域差やプランによって変動するため、こちらも間取りや土地がある程度決まった時点で、概算として見積もりに含めてもらい、ローン借入額の計画に組み込みましょう。
<2> 新築での“総額表記”が難しい理由
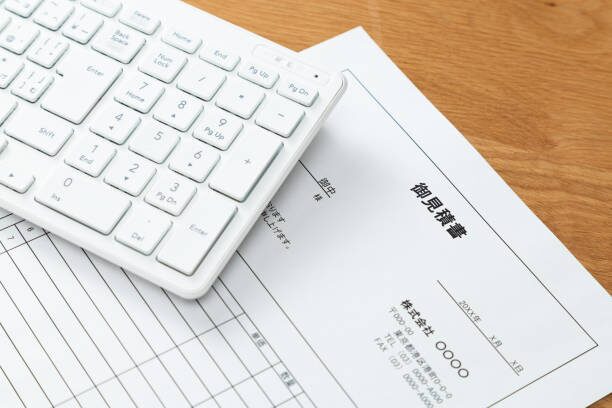
新築住宅の価格を「総額表記」で示すことが難しい理由は、上記で解説したように建築費用が多くの可変要素によって構成されるためです。
家はスーパーなどで購入する単品モノと異なり、一品一様です。
建物本体価格は図面や仕様が決まらなければ確定せず、付帯工事も間取り・土地の条件によって引き込みの距離が変動したり、地盤の強度・造成の有無などでも数十万〜数百万円単位で変動します。
さらに、外構やカーポートといったプラスアルファの要素は標準的に最初の見積では含まれない場合がほとんどです。
そのため、後から追加になるケースが多く、これらも「思ったより費用がかかった」という要素になりかねません。
諸経費についても、ローンか現金か?登記の方法、保険の加入条件などで差が出ます。
こうした事情から、広告やモデルハウスに表示される価格はあくまで「建物本体のみ」のことが多く、実際の支払総額とは乖離があります。
総額を正確に出すには、土地条件・仕様・付帯設備・手続き内容など、すべてを固めたうえで見積もりを取る必要があり、注文住宅の「とっつきにくさ」がここに集約されています。
<3> 7:2:1の概算法則

新築住宅の総費用をイメージする際に役立つのが「7:2:1の法則」です。
これは、建物本体価格:付帯工事:諸経費の割合をおおまかに示したもので、全体を10とした場合、建物本体が約7割、付帯工事が約2割、諸経費が約1割という考え方です。
例えば、建物側にかける総額を 約2,800万円 を目途に設定したとしましょう。
その場合、建物価格が1,960万円、付帯工事は約560万円、諸経費は約280万円が目安となります。
また付帯工事には、地盤改良・外構・水道・ガスの引き込みなどの費用が含まれ、土地条件によってはこの法則から大きく外れるケースもあります。
諸経費には登記費用、ローン関連費用、保険料、各種申請費などが含まれます。
なお、建物本体価格に合わせて付帯工事や諸経費は比例して上がる傾向にあるものの、建物本体価格の金額(比重)が高くなっていくと比率の法則から外れていくため、あくまで目安程度で考えましょう。
ただ、最初の資金計画を立てるうえで「建物価格 + 3〜4割程度の費用が必要」という意識を持つことが重要です。
これにより、“想定外”の予算オーバーや住宅の総額が見えにくい、という不安感が少し消えるのではないでしょうか。
<4>エツサスでは総額表示(概算)でのご案内も可能

このように新築住宅の価格は、土地条件や仕様、付帯工事の内容によって変動するため、一般的には最初の時点で「総額表示」をすることが難しいとされています。
しかしエツサスでは、あらかじめ間取り・仕様が決まっているプランをご用意しているため、初期段階から概算の総額をお伝えすることが可能です。
規格プランでは、必要十分な性能・設備を標準仕様として設定しており、大きな追加や変更がない限り価格変動が起きにくい点がメリットです。
また、その標準性能の高さによって保険料が安いことなども、隠れたメリットになります。
<4-1>総額イメージを早い段階で掴んでいただける

最初から間取りや仕様が決まっている、と聞くと少しネガティブなイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、この仕組みでは「建物本体価格」に加え、「付帯工事」や「諸経費」を含めた総額イメージを早い段階で把握できます。
さらに土地の条件や工事内容がある程度確定していれば、地盤改良や外構の目安費用も反映した、より現実的な資金計画を立てることが可能です。
これは、契約後に思わぬ追加費用が発生して、予算を圧迫するリスクを減らすうえで大きなメリットになるでしょう。
また、総額表示でのご案内は「住宅ローンの借入額を決めやすい」という点でも好評です。
毎月の返済額や返済期間を早期にシミュレーションできるため、家計への影響やライフプランとの整合性を確認しながら安心して家づくりを進められます。
まとめ

今回のコラムでは、新築の価格として「建物本体価格」「付帯工事」「諸経費」の3つで構成され、目安として7:2:1の割合となることを紹介しました。
土地条件や仕様の選択、インフラ状況によって費用は変動するため、広告に記載される価格と実際の支払総額が一致するとは限らない点も注意点です。
エツサスでは、間取り・仕様があらかじめ決まったプランもありますので、付帯工事や諸経費を含めた概算総額を早い段階でご案内できます。
新築は期待・希望が大きいイベントではあるものの、住宅ローンの借入額や返済計画という不安要素も大きいため、事前のシミュレーションで予算オーバーや追加費用による不安を減らすことが大事です。